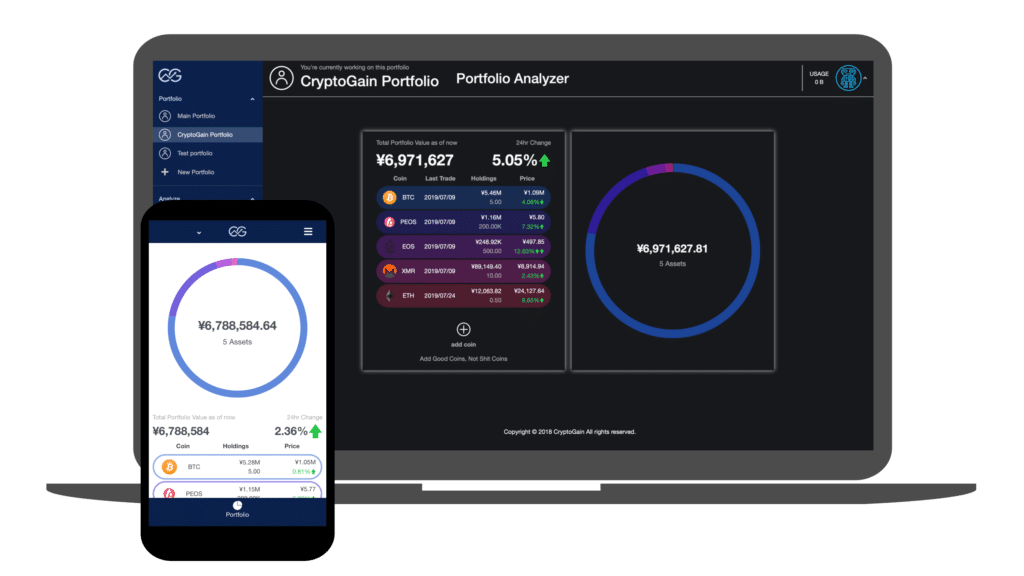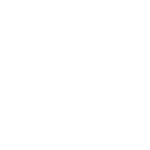日本基準と大きく異なり早くもGAAP差が
仮想通貨の会計処理について、2019年の12月に米国公認会計士協会(AICPA)は “Accounting for and Auditing of Digital Assets(デジタルアセットの会計と監査)”と題されたガイダンスをリリースしました。
原文は下記のリンクからダウンロードできます。
この指針は正式な会計基準ではないものの、AICPAがリリースしているということで米国基準(USGAAP)に基づく会計処理を行う場合は参考にされるのは間違いないでしょう。
日本基準(JGAAP)に関しては2018年3月に「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」がABSJ(企業会計基準委員会)からリリースされています。
クリプトに関する日本の会計基準については過去の記事で解説しています。
日本から二年近く遅れる形でアメリカのデジタルアセット(以下、クリプト)に対する会計の考え方が明らかになったわけですが両者の間には大きな違いがあります。
会計基準差をGAAP差といいますが、クリプトに関しては早くもJGAAPとUSGAAPとの間に大きなGAAP差ができたといえます。
今回は個人的に最も大きいと思われるGAAP差にフォーカスしたいと思います。
その違いはクリプトの評価に関連します。
具体的なGAAP差を見る前に今回のAICPAのガイダンスを読んで個人的に面白いと思った点についてまず紹介します。
Ether(ETH)は証券ではないとAICPAは考えている
ガイダンスのQuestion 1では、特定の業種に関するガイダンスを適用していない企業(簡単に言ってしまえば金融機関以外の普通の会社)が、現金で購入したクリプト・アセットをどのように会計処理すべきか?が問われています。
そしてここでいうクリプト・アセットとは以下のような特徴を持ったデジタルアセットとしています:
- どこかの監督官庁によって発行されたものではない
- 保有者とそれ以外の当事者との間に契約関係を発生させない
- 1933年証券法、1934年証券取引法における証券に該当しない
面白いのはこれらの特徴をもつクリプト・アセットとしてビットコイン、ビットコイン・キャッシュ、そしてイーサリアムが例示されている点です。
ビットコイン、ビットコイン・キャッシュについては証券か証券でないかという議論は通常おきません。
しかしイーサリアム関してはICOによる資金調達をしていたり、ICOを行った段階ではプロダクトがリリースされていなかったり、開発者の影響が強かったりと証券性が強いとする議論が未だ根強く残っています。
過去に米証券取引委員会(SEC)はセキュリティ・トークンだったものが実態の変化によってユーティリティ・トークンに変わることもあり得る(逆もしかり)としているのでそのような考え方が今回のガイダンスの作成にあたって考慮されたものと思われます。
いずれにしてもSECが未だイーサリアムの証券性について明確なスタンスを表明していない中、AICPAがイーサリアムを証券ではないと言い切ったことは面白いと感じました。
クリプト・アセットはUSGAAPでは無形資産として会計処理される
上述のとおり、ガイダンスのQuestion 1は現金で購入したクリプト・アセットをどのように会計処理すればいいかについて回答しています。
そこでの結論はビットコイン、ビットコイン・キャッシュ、イーサリアムのようなクリプト・アセットは無形資産として処理すべき、としています。
FASB ASC Master Glossaryにおいて無形資産は次のように定義されています:
“物的な実態の存在しない資産(金融資産除く)”
そして、これらのクリプト・アセットはUSGAAPにおける他の資産の定義に該当しないため無形資産以外の資産として会計処理することは適切でない可能性があるとしています。以下で、クリプト・アセットが他のそれぞれの資産になぜ当てはまらないかを、見ていきます。
現金あるいは現金同等物
クリプト・アセットがリーガル・テンダー(法定通貨)として国家による裏付けがない場合、現金同等物の定義に該当しないとしています。
金融商品あるいは金融資産
クリプト・アセットが現金でなく、法人の持分でなく、現金あるいは他の金融商品を受け取る契約上の権利でない場合は金融商品あるいは金融資産の定義に該当しないとしています。
棚卸資産
クリプト・アセットは通常の営業活動における売却のために保有される場合もありえるが、有形資産ではないため棚卸資産の定義に該当しないとしています。
USGAAPで無形資産はどのように処理するか
無形資産は耐用年数が確定できる場合はその期間に応じて償却しますが、クリプトの場合は耐用年数が決定できない場合がほとんどです。
その場合は非償却無形資産に該当し毎期の償却は行いません。
そしてこれが一番のポイントになりますが、クリプトの時価が値上がりしても時価評価しません。
日本の会計基準ではクリプトは基本的に時価評価することになるため大きな違いとなります。
では保有するクリプトの時価が取得原価を下回った場合はどうするか。
この場合は減損を検討することになり、基本的には簿価の切り下げを行います。
USGAAPでは減損の戻入は認められていないため一度切り下げた簿価は時価が回復しても切り上げることはしません。
クリプト会計基準の今後
この数十年の各国の会計基準の大きな流れは国際的なコンバージェンス(収斂)だったため、クリプトという新しい論点に関して早くもGAAP差が生じているのは面白いポイントです。
どちらの基準も既存の会計の枠組みになんとかデジタル・アセットを当てはめようと知恵を絞った結果だと思います。
本来会計基準は経済実態を表現するようにデザインされなければなりません。
新しいサービスや契約形態などが登場するたびにそれらの経済実態を表すベく会計基準は今までも変化してきました。
世の中を大きく変えてしまうほどの技術が登場した場合、会計基準の微調整だけではその実態を表現できなかったとしても不思議ではありません。
クリプトも第一世代がペイメント・カレンシー系だとすると第二世代のプラットホーム系とこの10年で多様化しています。
プラットホーム系のクリプトは値動きのエクスポージャーや決済のために使うのではなく、そのブロックチェーンプラットホームを利用するために保有するものがあります(ETHなど)。
この場合FVTPL(PLを通した時価評価)はもしかしたら実態を現しておらず、FVOCI(その他包括利益を通した時価評価)や無形資産のような処理が実態を現しているのかもしれません。
一つ一つが固有の資産であるNon-Fungible Token (NFT) を利用したデジタル・キャラクターやデジタル・アイテムなどを購入した場合はその購入意図によって棚卸資産や無形資産として処理するほうがより実態に近いといえます。
そしてビットコイン。
国家による裏付けがある通貨よりもプログラム、コンピューター、電力による裏付けがある通貨を選択する人が増え始めています。
その場合、法定通貨と同じように現金として処理するほうが実態を表すケースも増えてくるはずです。
その事業活動をビットコイン中心で行っている会社の機能通貨(Functional Currency)は法定通貨ではなくBTCかもしれません。
そのような世界を今想像することは難しいですが、この10年のクリプト・ブロックチェーンの進化を見ているとそう遠い未来でもないのかもしれません。